美しさを解き明かす学び
寺田寅彦『科学と科学者のはなし』を読んで
学生時代、理数系の科目はまったく得意ではありませんでした。
それなのに、こんなにも夢中でページをめくってしまうなんて。
今回ご紹介したいのは、
物理学者・寺田寅彦によるエッセイ集
『科学と科学者のはなし』です。
彼は夏目漱石の弟子でもあり、
随筆家としても知られる明治生まれの物理学者。
科学の話をしているのに、
まるで詩のようで、哲学のようでもあり、
ときに人情深くて、ふっと笑ってしまうようなユーモアさえある。
こんなふうに科学を語れる人がいるんだ…!
それが最初にこの本を読んだときの、正直な感想でした。
ー茶碗の湯と台風の共通点ー
たとえば、こんな話があります。
朝、湯呑みのお茶をすすりながら、
「この渦の動き、台風と似ているな」と気づく。
そして本当に、茶碗の中の湯と、
地球規模の台風が同じ物理法則で動いていることを
わかりやすく説明してくれるんです。
なんてことない日常の中に、
自然の法則が静かに潜んでいる。
そのことを、寅彦は当たり前のように、
でもとてもやさしく教えてくれます。
ー美しさを解き明かす学びー
私は、これまで布や写真、洋服、バッグなど、
いろいろな“ものづくり”に関わってきました。
「どうして美しいと感じるんだろう」
そんな問いから素材や構造に興味を持ち、
気がつけば自分で作るようになっていた。
その感覚と、寅彦が語る科学の世界は、
とてもよく似ています。
物理も、化学も、数学も。
すべては自然のしくみを解き明かす学び。
つまり、この世界の美しさを読み解く方法なのだと
気づかされました。
ー人や組織を見るまなざしにもー
このエッセイのなかには、
「津波と人間」や「線香花火」
「夏目漱石の思い出」など、
科学だけでは語りきれない、
人間へのまなざしが込められた文章もあります。
理系が苦手だった私にとって、
科学はどこか遠い世界の話でした。
けれど、寺田寅彦さんのまなざしはとても身近なものだった。
世界を観察するその視点には、人間らしさが宿っていて
目に見える現象の裏側にあるしくみを、ていねいに見つめ、言葉にしていた。
その姿勢は、人や組織と向き合うときにも、大切な視点だと感じました。
「なぜそうなるのか」
「何が起きているのか」
感情や関係性といった“目に見えない動き”を、
そのままにせず、言語化し、伝え合う。
それはきっと科学者の仕事も、組織づくりにも、通じるもの。
そんな発見があった一冊でした。
ーあとがきー
明治の終わりに生まれ、
昭和の初めにこの世を去った寅彦の言葉。
けれど、不思議なほどに、
いまの私たちにすっと寄り添ってくれる。
科学は、やさしい。
そして、美しい。
そのことを静かに教えてくれる一冊でした。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
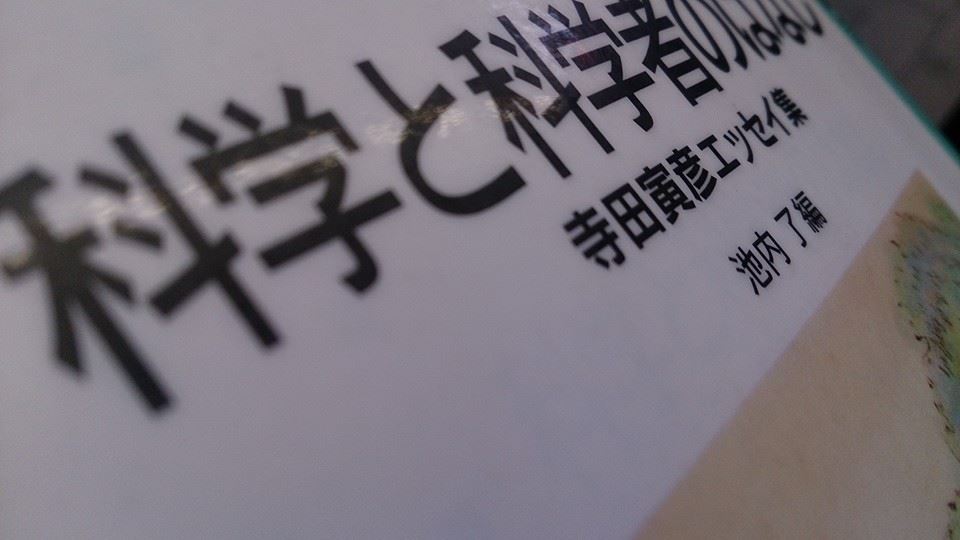
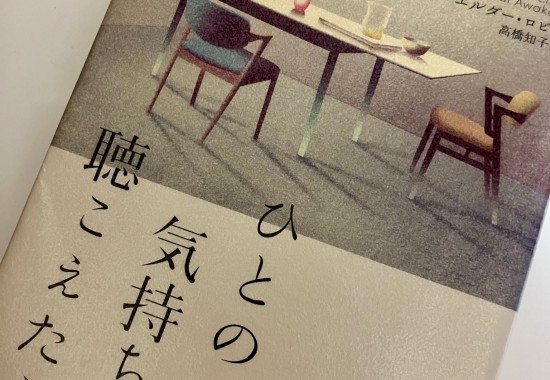
この記事へのコメントはありません。